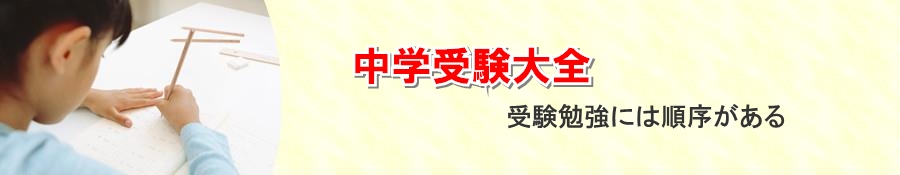知っている言葉も、違う意味で使われることがある。
更新日:

国語の問題文を読んでいると、たまに普通の言葉がカッコつきで書かれていることがある。
たとえば、「私は彼のことを『先生』と呼んでいた」等という風に、特定の単語にカッコをつけた文章だ。
このカッコ付きの言葉のことを特に「個人語」などと呼ぶことがある。
個人語というのは、一般的な言葉を、作者独特の定義で使っている言葉のことだ。
一般的な意味ではなく、特別な意味で使っているよ、と言うことを示すために、わざわざカッコをつけて表現している。
英語だったら、”the”をつけるところなのだが、日本語には定冠詞というのがないので、カッコで囲むことによって、特別感を表している。
例文として出した『先生』というのは、一般な先生とは違った意味で使われているので、設問でもこの『先生』について、色々問われることになる。
なぜ主人公はその人を『先生』と呼んでいるのかとか、『先生』と呼ぶ気持ちだとか、色々問題が出るわけだ。
こういう風に、一般的な言葉やモノであっても、特別な意味を持つのが個人語だ。
そして一般的な言葉が、正反対の意味を持つ場合もある。
たとえば犬を見たときに、ニコニコして寄っていく人と逆に怖がって逃げて隠れる人がいる。
全く同じ犬を見ているのに、なぜこういう違いが起こるのだろう?これは犬に付けられたイメージが、人によって異なるからだ。
前者は、犬に「可愛いもの」というイメージを持っている。
後者はは、犬に「怖いもの」というイメージを持っている。
なので全く同じ犬を見たとしても、反応が正反対になってしまうわけだ。
なので問題文中に犬という言葉があっても、作者は可愛い動物だとは思っていないかもしれない。
個人語が分かっていないと、答えを間違えてしまうわけだ。
フェルディナンド・ソシュール

個人語は、一般的な言葉に対して、作者独自のイメージをつけたものだが、言葉というのは元々、勝手に作ったもので、その言葉によって世界の見方は変わってしまう。
これはフェルディナンド・ソシュールというスイスの言語学者が言い始めたことらしい。
ソシュールは19世紀から20世紀に生きた人だが、近代言語学の父と呼ばれ、「各民族語は相互に異なる固有の世界像を持つ」と言う考え方を示した。
我々の知っている世界というのは、実は言葉によって有り様が決まり、「世界は言葉でできている」。
言葉があるからモノを区別することができるし、言葉がなければその言語圏では無いものになる。
たとえばよく聞く話だが、虹の色はイギリスでは6色だという。
他にも2色とか3色だという文化もあるらしい。
となると、虹の色を尋ねられたら、ある国や言語圏では6色とか7色を答えるが、他の国や言語圏では2色や3色しか思いつかないのだ。
同じ地球上に生きて、同じ虹を見ているはずなのに、なぜこんな違いが生まれるのかというと、言葉によって勝手に境界線が引かれているからだ。
たとえば、食品表示で問題になっていたサーモン(鮭)とトラウト(鱒:マス)は、生き物としては大きな違いはない。
なので鱒の仲間のニジマスやマスノスケをサーモン(サーモントラウト/キングサーモン)として販売したり、寿司ネタとして使っているわけなのだが、鱒は鮭ではないから偽装表示ではないか?と言われて問題になっているわけだ。
ところが日本で鮭と呼ぶシロザケは、もともと英語で言うサーモンではなかった。
イギリスが世界各地に植民地を作っていく過程で、各地のサーモンに似た魚に○○サーモンと名前をつけた結果、日本の鮭もサーモンの一種だとされただけだ。
一方、日本は日本で、サケマス類に、独自に○○マスという名前をつけていったので、日本語では、ニジマスやマスノスケは、マスの一種だが、英語ではサーモンの一種でトラウト(マス)ではないというように食い違いが起こったわけだ。
こういう風に、言葉は世の中に境界線を引いていて、その境界線の中で我々は生きていると言うことらしい。
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
楽天ブックス(広告)